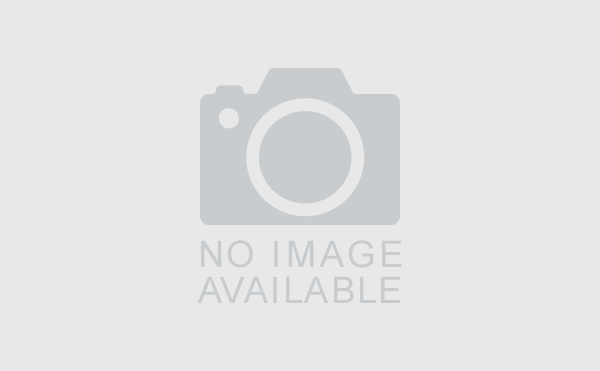二次性多汗症
二次性多汗症は、別の病気や状態が原因で過剰に汗をかく症状を指します。原発性多汗症が特定の原因なしに発症するのに対し、二次性多汗症は通常、他の健康状態や外的要因が引き金となって発症します。
二次性多汗症の特徴
-
全身的な発汗:
- 原発性多汗症とは異なり、二次性多汗症では、発汗が特定の部位に限定されず、全身的に過剰な汗がかかることがあります。
-
発汗が一定のパターンで起きる:
- 発汗が特定の時間帯(例えば夜間)や特定の状況(例えば食後や運動後など)に強くなることがあります。
-
発汗の原因が外的な要因:
- 発汗を引き起こす病気や状態があるため、その治療をしない限り、多汗症は改善しません。
二次性多汗症の原因
二次性多汗症の原因は非常に多岐にわたりますが、主な原因として以下のようなものがあります:
1. 内分泌系の疾患
- 甲状腺の異常:甲状腺が過剰に働く(甲状腺機能亢進症)と、体温が上がりすぎて発汗が増加することがあります。逆に甲状腺機能低下症でも異常な発汗が見られることがあります。
- 糖尿病:特に低血糖時には発汗が異常に増加することがあります。低血糖は、糖尿病治療薬やインスリン治療を受けている患者でよく見られます。
- 更年期障害:ホルモンの変動により、特に女性に多く見られ、ホットフラッシュ(急激な発汗)や発熱感が頻繁に起こります。
2. 感染症
- 結核や肺炎、HIV/AIDS、風疹、インフルエンザなど、感染症の中には発熱とともに大量の発汗を引き起こすものがあります。
- 慢性の感染症は体温調節に影響を与え、発汗が増えることがあります。
3. 薬剤の副作用
- 特定の薬剤が副作用として過剰な発汗を引き起こすことがあります。たとえば、抗うつ薬や抗精神病薬、降圧薬(血圧を下げる薬)、鎮痛薬などが関与することがあります。
- 抗コリン薬やベータブロッカーなども、体温調節に影響を与え、発汗を引き起こす場合があります。
4. がん
- 特にリンパ腫や白血病などの血液がんや一部の内臓がんでは、発熱とともに異常な発汗が生じることがあります。この発汗はしばしば夜間に強くなることがあります。
- 悪性腫瘍が体内にある場合、その成長や代謝の影響で体温調節が乱れ、多汗症が起こることがあります。
5. 神経系の障害
- 脳卒中や脳腫瘍、神経系の疾患などが原因となり、発汗の調節が障害されることがあります。
- パーキンソン病などの神経変性疾患でも、多汗症が見られることがあります。
6. 自律神経失調症
- ストレスや不安、過度な緊張などが原因で、交感神経が活発に働き、発汗が過剰になることがあります。自律神経が正常に機能していない場合にも、多汗症が引き起こされることがあります。
7. 肥満
- 肥満や体重過多は、体温を上げる要因となり、過剰な発汗を引き起こすことがあります。体脂肪が多いと、体温調節がうまくいかず、汗をかきやすくなります。
二次性多汗症の診断
二次性多汗症の診断は、原因となる疾患を見つけることが重要です。医師は、以下の方法で診断を行います:
- 病歴の確認:発汗のパターン、症状が現れる時間帯、生活習慣、服薬歴などを詳しく聞き取ります。
- 身体検査:異常な発汗がどの部位に現れているか、全身状態をチェックします。
- 血液検査:内分泌系(ホルモン)、感染症、糖尿病、血液疾患などを確認するために血液検査を行います。
- 画像検査:必要に応じて、CTスキャンやMRIを使って、神経系や内臓の異常を調べることがあります。
二次性多汗症の治療
二次性多汗症の治療は、根本的な原因を治療することが最も重要です。原因に応じた治療を行うことで、多汗症の症状も改善することが多いです:
-
病気の治療:
- 糖尿病の管理、甲状腺異常の治療、感染症の治療など、基礎疾患に対する治療が行われます。
- ホルモン療法や抗がん治療が行われる場合もあります。
-
薬物治療:
- 必要に応じて、抗コリン薬やβ遮断薬などが処方されることがあります。
-
生活習慣の改善:
- 健康的な食事や運動を心掛け、肥満の改善を目指すことが重要です。
-
対症療法:
- 発汗の軽減を目的に、デオドラントや抗汗スプレー、ボトックス注射などが使われることもあります。
結論
二次性多汗症は、病気や外的要因が原因で過剰な汗をかく症状です。発汗の原因となる病気を特定して治療することが最も重要です。
投稿 二次性多汗症 は メプラス - MEPLUS に最初に表示されました。