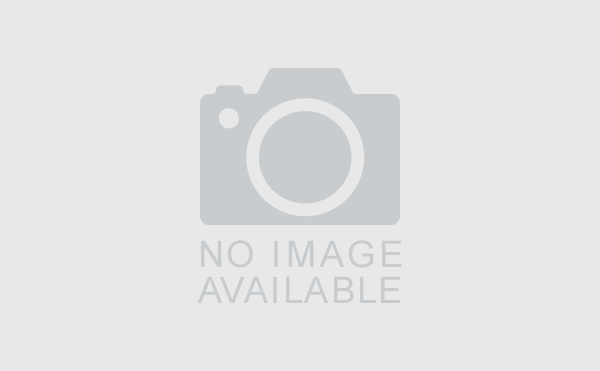1型糖尿病の治療方法
【1型糖尿病の治療】
1. インスリン療法(必須)
1型糖尿病では体内でインスリンが作られないため、生涯にわたり外から補う必要があります。
インスリンの種類:
- 超速効型(例:ノボラピッド、ヒューマログ)
→ 食事直前に使う。効果は5〜15分で発現し、2〜4時間で消失。 - 持効型(例:ランタス、トレシーバ)
→ 1日1~2回、24時間程度持続し、基礎インスリンとして使う。
インスリン投与方法:
- 1日4回注射(強化インスリン療法)
- 食前3回+就寝前or朝の持効型1回
- インスリンポンプ(CSII)
- 皮膚にカテーテルを挿入し、常時少量のインスリンを自動注入
【血糖管理】
1. 自己血糖測定(SMBG)
- 指先から血を採って測定
- 1日4回以上が目安
- 食前・食後・運動前後など状況に応じてチェック
2. 持続血糖モニタリング(CGM)
- 皮下に小さなセンサーを装着し、24時間リアルタイムで血糖変動を記録
【最新のインスリンデバイス】
| デバイス名 | 特徴 |
|---|---|
| インスリンポンプ(例:ミニメド、オムニポッド) | 微量のインスリンを持続注入。設定によりボーラス(食事時)も自動注入可能。 |
| 持続血糖測定器(CGM) | Dexcom G7 や FreeStyleリブレ。針を刺すことなくスマホなどで血糖値確認。 |
| SAP(Sensor Augmented Pump) | CGMとポンプが連動し、血糖が下がりすぎると自動停止。 |
| 自動インスリン注入システム(AID) | AIが血糖変動を予測し、インスリン量を自動調整する次世代技術(例:ミニメド780G)。 |
【生活の工夫】
1. 食事管理
- カーボカウント(Carb Counting):
摂取する炭水化物の量を把握して、それに応じたインスリンを打つ方法 - バランスの取れた食事、GI値(血糖上昇速度)の低い食品を選ぶ
2. 運動
- 有酸素運動(ウォーキング、スイミング)は血糖を下げる作用
- 運動中や後の低血糖に注意し、事前の血糖測定と補食が大切
3. 低血糖対策
- 症状:冷や汗、動悸、ふるえ、空腹感、意識混濁など
- すぐにブドウ糖やジュース(10〜20gの糖分)を摂取
- 周囲の人にも説明しておき、緊急時対応を共有しておく
【生活で心がけること】
- 無理せず、ストレスの少ない生活を
- 旅行や外食時はインスリン・補食・血糖測定器を忘れずに
- 病気時(風邪、発熱など)も血糖値が変動しやすくなるので注意
- 医療者との定期的なフォローアップも重要(HbA1c、合併症検査)
ご希望であれば、以下も詳しく解説できます:
- カーボカウントの実践方法
- インスリンポンプとCGMの機種比較
- 子ども・学生の1型糖尿病との付き合い方
- 保険制度・福祉サービスの活用
投稿 1型糖尿病の治療方法 は メプラス - MEPLUS に最初に表示されました。